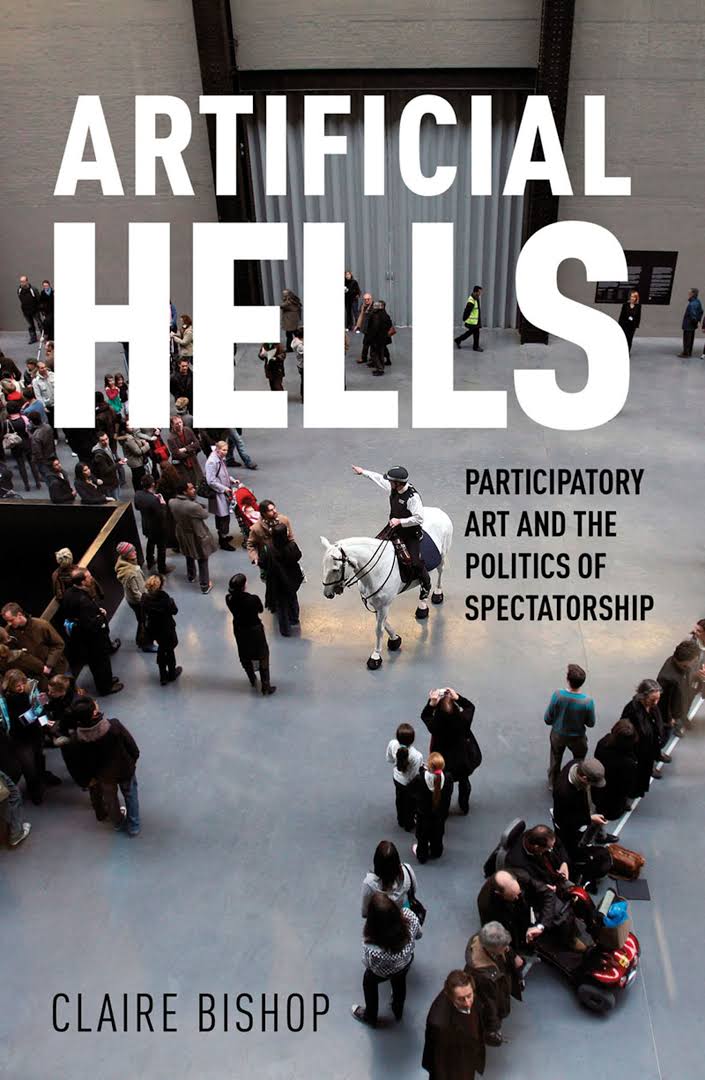ヨーロッパ・フェスティヴァル文化から岡田利規/チェルフィッチュが受けた歓待を理論化/歴史化する―「横断=貫網の詩学」と「委任されたパフォーマンス」*
序
過去十年以上にわたって、時に応じて書き綴ってきたように1、劇作家・演出家の岡田利規が主宰するチェルフィッチュが2007年の五月、ヨーロッパのフェスティヴァル文化サーキットのひとつにおいてセンセーショナルな話題を提供したことにつき、わたしはどう考えてよいのか、知的な障壁とでも呼ぶべきものに、ぶつかっていた。それはベルギーのクンステン・フェスティバル・デザール(以下、クンステンと表記)における出来事だったが、そこで上演された岡田利規作・演出による『三月の5日間』(2004)が熱狂的に迎えられ、それ以降チェルフィッチュには、大陸ヨーロッパのフェスティヴァル・サーキットを中心として、50以上の上演のオファーがあったというのである2。当時の日本において岡田利規とチェルフィッチュの存在は、岡田が同作で岸田戯曲賞を受賞したとはいえ、メインストリームからまだ広く認知されてはおらず、せいぜい困惑をもたらすものと考えられていた3。チェルフィッチュを評価する一部、先鋭的な批評家間では、チェルフィッチュの上演がダンスなのか演劇なのかといったジャンル論的議論が起きていたが4、わたし自身はそうしたジャンル決定論的議論にそれほど興味があったわけではない。というのも、そうしたカテゴリー分けをしたいという欲望そのものが、遅れてきた近代的なものとしか、少なくとも当時は思えなかったからである。そして、その、カテゴリー分けしなければすまないという緊急性がなぜ生じるのかといえば、その淵源にはゼロ年代特有の〈ナショナルなもの〉との微妙な関係があるのではないか。すなわち、劇作家としての岡田の戯曲テクストにおける口語日本語のエクリチュール的探求と、演出家としての岡田による書かれた言葉とパフォーマーの身体の関係性の更新を伴うチェルフィッチュの上演が、制度化されてはいても魅力的でありえる日本の〈ナショナルなもの〉というトロープの範疇にある政治/社会/文化的なローカルなものへ、あるいは、たこつぼ的な穴へと、より深く沈潜しているものとして発想されているからこそ、ジャンルを確定する=定義をするという欲望を喚起しているのではないか、とわたしはその当時、考えていたのである。既存の、非日本語圏市場向きに〈日本〉をブランド化したものではない、新たな〈ナショナルなもの〉のさぐりだとみなしていたと言い換えてもよい。たしかに、岡田の上演にエキゾチックだったり伝統的だったりする要素は何もなく、歌舞伎や能、あるいはいわゆる暗黒舞踏との関連性―はたまたそこに、蜷川幸雄による空虚で装飾的かつ情緒的な西洋古典の上演を加えてもよい―を想起させるものなど何もなかったのである。さらにいえば、近年グローバルな人気を獲得したとされる〈クールジャパン〉とひとくくりに呼ばれることもある日本の〈サブカル〉諸ジャンルとの関連を考えてみても、岡田の方法論は、たとえば、村上隆による伝統と同時代、あるいは大衆文化と芸術を、欧米の美術市場をターゲットにして、意識的に雑種化するという戦略とも、共通点を見出すことはむずかしかった。岡田利規/チェルフィッチュの出現は、あくまでも同質であることが前提である、わたしが〈Jという場所〉と呼ぶ閉域内の出来事―方法的には画期的であるにせよ―だとわたし自身は考えていたのである。だからこそ、岡田/チェルフィッチュの大陸ヨーロッパにおける〈成功〉は、大きな衝撃をわたしにもたらしたのだった。

『三月の5日間』を招聘したクンステンの芸術監督、クリストフ・スラフマイルダーは、2008年に行われた岡田利規との対話において、日本語による上演という言語の問題があったため、ブリュッセルにおける『三月の5日間』では、ある一定の要素が失われたとしつつも、こう続けている。
純粋に直接的な身体の提示の仕方ということ自体は、(略)新しいものではありません。しかし、それを岡田さんの作品におけるような形で見るということは新しいことでした。分節の仕方が私にとって新しかったのです。これは比喩的にも文字通りにも分節の問題であり、したがって身体と言語を通して現実を分節するということさえ可能だと思います。この分節法は見たことがないものでした(以下略)
(Slagmuylder 2008: 6, 9)

熱狂的にチェルフィッチュを大陸ヨーロッパに迎え入れたのは、日本の〈伝統文化〉や村上隆のネオポップな美術に飽きた人たちだったのかもしれないが―この点については、後述する―スラフマイルダーは、岡田の「身体と言語を通して」の「現実」の「分節」が新しく、その分節法を「見たことがないものだった」としている。つまり彼は、まったく異なるものではなく、パフォーマンス文化における同じ土俵の上、同じパラダイムの内部で評価可能なものとして、あるいはジェイムス・ハーディング(James Harding)とジョン・ラウス(John Rouse)が編集した書物のタイトルを使うならば、「また別のアヴァンギャルドではない(not the other avant-garde)」(cf. Harding 2006)ものとして、岡田/チェルフィッチュを招聘したというのだ。そして、その後岡田/チェルフィッチュが大陸ヨーロッパのみならず、世界各地で受け入れられていったことを考えると、スラフマイルダーの招聘の決断は正しかったと言うべきなのである。
- 1∧わたしが岡田利規/チェルフィッチュについて初めて書いた文章は、『三月の5日間』初演(2004年2月)直後、「図書新聞」に掲載された劇評「Jと世界を語り直す――チェルフィッチュ『三月の五日間』」だった(Uchino 2004)。そこでわたしは「この作品で重要なのは、(略)〈パフォームする身体〉自体が、イラク攻撃前後の東京というきわめて政治的な文脈に解き放たれていることだろう。つまり、岡田の興味は、単にフォルマリスムの実験にだけあるのではない。この作品で彼は、言葉と身ぶりがずれるという身体的リアリティを生きる〈Jという場所〉の住人が、どのような関係を生かされているのかを、物語的設定を使いながら、ヴィヴィッドにマッピングするのである。なかでも〈Jという場所〉と『世界』の距離が緻密に測量されていることは印象的である。こうしてこの上演は、『語るべき物語』など何もないと開き直ることなく、語りの方法それ自体を問い直すことで『語るべき物語』はいくらでもあると宣言するのである」と書いていた。
- 2∧岡田利規/チェルフィッチュの当時の制作者中村茜氏(現、株式会社precog代表取締役)との個人的な対話による。
- 3∧2005年に第49回岸田戯曲賞を受賞したのちの岡田は、同年7月『クーラー』で「TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD 2005―次代を担う振付家の発掘―」最終選考会に出場。また、07年デビュー小説集『わたしたちに許された特別な時間の終わり』を新潮社より発表し、それが翌年第2回大江健三郎賞受賞する(https://chelfitsch.net/profile/)など華々しいと呼べる活躍をしていた。しかし、日本の演劇界では、新国立劇場における『エンジョイ』(作・演出、06)とデーア・ローアー『タトゥー』(演出、09)、あるいは、世田谷パブリックシアターにおける安部公房『友達』(演出、08)等が評価されたとはいえず、その後こうした公共劇場での上演から岡田は遠ざかることになる。そのことには、日本特有の国内的演劇市場とそこにおける交換価値の問題、つまりは、ガラパゴス的なマーケットが全体化しているという問題が深く関係している。その内部では、政治性や演劇美学にかかる闘争があり(あるいは、あることになっており)、そこに帰属する者たちは、その圏域での差異/階層/乗り越え運動のダイナミズムを前提に、自分たちが閉鎖的だなどとはまったく思ってはいないという特殊性がある。そのため、岡田/チェルフィッチュのような、パラダイムシフトをもたらしかねない、つまりは、埒外の外部については、通常、全否定で対応する(=「あれは演劇ではない」)ことが多い。他方、岡田/チェルフィッチュはその後、主として大陸ヨーロッパの演劇祭の共同制作によるクリエーションを中心にしていく。その最初は、クンステン・フェスティバルにおける成功の翌2008年、ヨーロッパの三つの演劇祭(KUNSTENFESTIVALDESARTS(ブリュッセル)、Wiener Festwochen(ウィーン)、Festival D’automne(パリ))からの委嘱によって創作された『フリータイム』である。つまり、クリエーションにかかる経費をこれらの演劇祭が基本的に負担することになった、ということである。
- 4∧註3で触れたように、岡田が、05年7月『クーラー』で「TOYOTA CHOREOGRAPHY AWARD 2005―次代を担う振付家の発掘―」最終選考会に出場したとき、審査委員会において同作品がダンスか演劇かという議論があり、ネット上で、そういう議論がある程度、進行したと記憶している。ネット上の個人ブログ等での出来事であり、散発的で記録を辿ることが難しいが、よくまとまったオフィシャルなネット上の記事としては、Ozaki 2002を参照のこと。
1.普遍性か、さもなければ
岡田がその後もヨーロッパその他の地域で〈成功〉をとげるにつれ、学術的言説も書かれるようになってきた。そのうち、日本を拠点にして活動する美術評論家の松井みどりは、表象文化論学会の学会誌『表象』第五号(2011)に掲載された「両面通行―グローバル化時代の国際展と日本の現代美術の受容」(Matsui 2011)において、岡田作品がヨーロッパ及び北アメリカで受容されたことにつき、説得的な議論を展開している。論考のタイトルが示すように、本論は、グローバル化に対応して動きはじめていた日本の現代美術―それを象徴するものには、国際展や間文化的市場において、論じられることが多くまた論争を呼んでもいた村上隆の仕事がある―についての議論が、その中心をなしている。しかし、本論の終わり近くで松井は、小沢剛やChim↑Pomといったよく知られた美術家や美術家集団を論じる延長線上で、岡田の作品を取りあげるのである。
2007年から2010年にヨーロッパ及び北アメリカで書かれた多くの批評を検討した結果として、アメリカ・ツアーについて書かれたある劇評に言及しつつ、次のように松井は言っている。
そして、予想通りというべきか、ジル・ドゥルーズを引用しつつ、岡田の上演で共有され、評価された彼の方法においては、「思考と身体の微細な運動の他との接触のなかで築かれる反応の無意識の型をとおして立ち上がる、流動的な主体の表れが示されているのだ」(同上)と書く。
他方、同誌同号に掲載された海外における日本の現代アート実践の受容についての討議において、また、未出版の英語論文「”Database Animals” and the Avant-garde: Materializing Transnational, Transient Subjectivities in Posthumanity(『データベース的動物』とアヴァンギャルド―ポストヒューマニティにおけるトランスナショナルで一時性の諸主体を物質化する)」やその他の論考において(cf. Uchino 2008, 2015)、わたし自身も岡田の作品とそれが日本語圏の外で広く受容されていることにつき、同じような批評的視点から論じている。単純化を恐れずいうならば、そこでわたしは、岡田作品が、オリエンタリズムとかかわらない、非時代的に見える普遍的熱狂を喚起している理由のひとつとして、その上演の主題が何であれ、「ポストヒューマニティにおけるトランスナショナルで一時性の諸主体」を、岡田の創出する演劇的時空間にパフォーマティヴに登記することを可能にするその方法にあると主張している。
同じ問題について、別のアプローチを試みた日本語論文もあり(Uchino 2010)、そこでわたしは、パフォーマーの身体と言葉と音響と照明効果の関係が、統御されつつもより自発性へと傾斜させることへの、岡田の興味の深化について書いている。近年の岡田作品にたちあう観客は、その舞台で起きることに対し、劇場やパフォーマンス空間における習慣化した振る舞いから抜け出ることにより、身体的、知的、感情的に、あるいは、意識的であれ無意識的であれ、反応するあるいは応答することを求められる。そのように岡田は、パフォーマンスの物質性、あるいは演劇の〈いま、ここ〉をより複雑化しているのだと、わたしはそこで論じた。そのわたしの議論については、たとえば2014年に初演され、2015年5月11日にNHKによって全国放送もされた『スーパープレミアムソフトWバニラリッチ』の映像などでも簡単に確認できるだろう。これら一連の上演で観客は、俳優がなにかを〈する〉空間としての劇場という普遍的に了解された約束事(コンヴェンション)を仮定する一方で、以下のものへの応接を求められる。すなわち、俳優の動きや言表行為のひとつひとつ、彼/女たちのナラティヴ全体へのかかわり(作品の諸テーマや主題と呼ばれるもの)、周囲の環境(照明の光、音響効果、舞台そのものの物質性という、空間の物理的音響的ありよう)、文化的に同定可能な舞台の設定(最新作では、コンビニとそこを頻繁に訪れる日本の若者たち)、さらに、上演の瞬間瞬間に変化し続ける物質性、および、継続的かつ堆積的な瞬間瞬間に生起する諸情動、観客の目の前で、物理的、心理的、知的、あるいはその他の、微細に開示される瞬間瞬間。そういったすべてに、岡田/チェルフィッチュの観客は、いちいち応接することが求められるのである。

2.岡田利規とその「横断=貫網の詩学(transversal poetics)」
こうした思考の延長戦上で、松井の短いが実に的確な普遍主義的言説に換喩的にかかわるために、ここでブライアン・レイノルズ(Bryan Reynolds)の「横断=貫網的諸主体(transversal subjects)」という近年彼が展開してきた概念を導入することを考えてみたい。というのも、「横断=貫網的諸主体」とは、松井が参照するドゥルーズ的な「流動的な主体」、あるいはわたし自身の言葉では、「トランスナショナルな一時性の主体」をよりいっそう先鋭化させた概念であるだけでなく、元々シェイクスピア研究者であり、また、演出家でもあるレイノルズゆえの、広義の演劇あるいはパフォーマンスに深くかかわる概念でもあるからだ。そのため、岡田とチェルフィッチュがなぜ過去10年、ヨーロッパのフェスティヴァル文化から歓迎されてきたかをまた別の切り口から考えるために、必要な理論的ツールとみなせるのである5。
その『横断=貫網的諸主体―デリダのあと、モンテーニュからドゥルーズまで(Transversal Subjects: From Montagne to Deleuze after Derrida)』)(2009)のなかで、レイノルズは「横断=貫網的演技(transversal acting)」を以下のように定義している。
この一説はジャルゴンまみれであるし、レイノルズの造語も出てくるため、必要以上に難解であるように感じられる。しかし、少なくともわたしが理解した範囲では、ここでレイノルズが言おうとしていることは、岡田のより現在に近い作品について、そのパフォーマンス空間の複雑な物質性について考えるのに、有用なのではないか。
そのためにもわたしたちは、レイノルズの「なること(becomings)」と「なってしまうこと(comings-to-be)」という概念について理解する必要がある。したがってここでは、その定義を、長い引用になるが、参照しておきたい。
「なってしまうこと(comings-to-be)」:期待されるもの、概念化されたもの、さらに/あるいは望まれるもの(リアルであれ想像上であれ)以上のもの、あるいは異なるものに不注意にも変容してしまう現象。しばしばそれは、「なること(becomings)」の望まれた結果からの逸脱として起きる。「なること(becomings)」という意図的な活動を経験しているあいだにも、個人、カップル、グループは、自意識あるいはコントロールを失うことで、受動的に「なってしまうこと(comings-to-be)」を経験することが可能である。このことで、意図された「xになる(becoming-x)」という目的論から脱線させ、過剰なあるいはオルタナティヴな諸アイデンティ・コードや期待されない諸経験や諸主体性を生み出す。このような失敗や過剰は、擬似的権威(emulative authority)と見なされる諸形象(figures)との関係においてしばしば起きる。「なってしまうこと(comings-to-be)」はしたがって、あらゆる「なること(becomings)」のなかに潜在性として埋め込まれている。どちらのプロセスも多数的かつ不変であり、人びとの諸経験や諸表現を貫通してレイヤー化されている。というのも、どれだけの時間継続するにせよ、主体性は「なること(becomings)」と「なってしまうこと(comings-to-be)」との間とその中における諸交渉を通じて、瞬間瞬間の具体的現れをする(instantiates emergently)からである。
(273-4、強調は引用者)こうしてふたつの定義を見てみると、レイノルズの横断=貫網の理論は、日常生活においてであれ、芸術や演劇というフレーム内においてであれ、パフォームすることの一般的な理論としてそもそも読めるものだと理解されるだろう。演技論的に考えるなら、伝統的な演技の約束事(コンヴェンション)においては、すべては「登場人物になること(becomings-character)」―ここでの登場人物は単数形である―のためだと考えられている。レイノルズ的語彙を使うならば、横断=貫網的演技を「出来事化する(eventualized)」ためには、「なってしまうこと(comings-to-be)」が意識的に、あるいは戦略的に導入される必要が、あるいは劇場の時空において、仄めかされる必要がある。もしそうなれば、「なってしまうこと(comings-to-be)」は「目的論から脱線させ、過剰なあるいはオルタナティヴなアイデンティ・コードや期待されない諸経験や主体性を生み出す」。岡田/チェルフィッチュの上演的物質性が複雑であるのは、この「なってしまうこと(comings-to-be)」が意図的に導入されたこと、あるいは、それがパフォーマンスの時空において、戦略的に許容されたことによるのではないか、というのが、レイノルズの論を踏まえたうえでの本論の主張である。
岡田の「横断=貫網の詩学」を、また別の言い方、そしてレイノルズほど複雑な概念ではない用語にパラフレーズすることを試みるならば、それは、リチャード・シェクナー(Richard Schechner)によるよく知られた「わたし自身でない(not myself)……わたし自身でないではない(not not myself)」という演技の存在論との関係で論じることも可能であろう。すなわち、ここでレイノルズが「横断=貫網的演技」として理論化しようとしているのは、少なくとも演劇/劇場的文脈では、「なってしまうこと(comings-to-be)」としての「わたし自身ではないではない(not not myself)」が意識されることによって、流動的であるかどうかにかかわらず、演技的主体性が「瞬間瞬間、具体的現れをする(instantiates emergently)」ことが可能になり、その結果、その演技的主体性を、継続可能な特定の時空において、俳優と観客が共有することが可能になるということになる(それは登場人物などという同一性ではもちろんない)。
「擬似的権威(emulative authority)」としての岡田によって言語的に割り当てられた、あるいは事前に書き込まれた「登場人物になること(becomings-character)」と、〈発語―身ぶり〉のパフォーマンスに不可避的に生じる「なってしまうこと(comings-to-be)」の経験とのあいだにおける交渉を俳優自身が自覚的に経験する通路を、劇作家であり演出家でもある岡田が近年、その上演の時空間に、以前にもまして、正確かつ方法的に持ち込みつづけているのではないかというのが、わたしの議論である。このことが、とりたてて新しいとか革新的だとかわたしが考えているわけではない。というよりむしろ、「横断=貫網的演技」という新しい名称を与えられているにしても、演技の基本原理への回帰ではないか、とシェクナーを参考するならば、思われるのである。というのも、この原理そのものが、少なくとも欧米の文脈では、かなり長い間失われたと見なされてきたからである。その文脈では、登場人物というものは、「瞬間瞬間、具体的表れをする(instantiates emergently)」、すなわち、俳優と観客のあいだの時空のどこかに、間主観的かつ現象学的に(あるいは生成変化的に)、記載・登録されるものではなく、俳優が舞台上で実現するイメージ/表象/実体として、目的論的に、すなわち「登場人物になること(becomings-character)」のために処方された同一性であると、見なされてきたからにほかならない。
この失われた原理を再生するために、岡田は「登場人物になること(becomings-character)」という共有されるあるいは既知の約束事(コンヴェンション)から離れるように俳優に求めなければならない。すでに本論でも紹介した『スーパープレミアムソフトWバニラリッチ』のような最近の作品における岡田の俳優は、台詞を話すときに、その身体が音楽に―この作品ではヨハン・セバスチアン・バッハの『平均律クラヴィーア曲集』の第一巻―明確にしかし即興的に、応答ないしはシンクロすることが求められていた。音楽は、時空に限界づけられた現象学的存在あるいは現れの行為者性(エージェンシー)が、「意図された『xになる(becomings-x)』という目的論」から脱線し、「過剰なあるいはオルタナティヴな諸アイデンティ・コードや期待されない諸経験や諸主体性を生み出す」ための、字義通りの伴奏となっていたのである。

この事態については、「ノイジーな身体」といったようなターミノロジーで、岡田/チェルフィッチュを特徴付けるような数多くの日本語圏の言説と響き合うものがある6。しかし、これまでの議論で明らかなように、岡田/チェルフィッチュの「ノイジー」は、戦略的にもちこまれた「なってしまうこと(comings-to-be)」と言い換え可能であり、したがってそれは、単なる身体の揺らぎや統御不能性、あるいはそこから生じる「流動的な主体」(ドゥルーズ/松井)といった俳優の〈わたし〉―あるいは、「わたしではない……わたしではないではない」(シェクナー)―にかかわるイメージに留まるものではない。それは、観客とのあいだに瞬間瞬間生成する身体的、知的、情動的関係において、物語世界の登場人物(becomings-character)―『スーパープレミアムソフトWバニラリッチ』では、コンビニの店員とそこを訪れる客―とそこに収まらないもの、すなわち潜在性、あるいはノイズとしての「なってしまうこと(coming-to-be)」が、パフォーマンスの瞬間瞬間に、拮抗しつつ摩擦を起こしつつ融和しつつ乖離しつつ開示されつづける、岡田/チェルフィッチュのきわめて複雑な時間的空間的プロセスの呼称だと考えられるべきなのである。7
- 5∧ブライアン・レイノルズは1965年生れ。カリフォルニア大学アーヴァイン校教授。批評理論家、パフォーマンス理論家、シェイクスピア学者であり、社会理論とパフォーマンス美学及び「横断=貫網の美学」として知られる研究の方法論を組み合わせた領域を発展させた。彼はまた劇作家、演出家、パフォーマーでもあり、アムステルダムに拠点を置くアメリカとヨーロッパのアーティスト集団「横断=貫網の劇団(Transversal Theater Company)」の共同創設者でもある。この集団は彼の作品をいくつか上演している(https://en.wikipedia.org/wiki/Bryan_Reynolds、和訳は引用者)。今のところ日本語訳はなく、ここから論じていく”transversal”についても、定訳はない。”transversal”とは、複数の線と交差していく線的運動のありようであり、ここでは「横断=貫網的」ないしは「横断横断=貫網の」と訳した。なお「貫網」という訳語については、古典表象文化論・シェイクスピア学者の高田康成氏のサジェスションによる。「横切る」という意味合いを残すため、本稿では、変則的だが、「横断=貫網」という表記にしている。イメージ的には、上下ではなく、横への運動性/移動性であることが重要で、「横断=貫網的演技(transversal acting)」とは、その瞬間瞬間に変化する自身の内外(内面/心理、身体、及び上演の諸環境)と自覚的(そこには、直感的という感覚も含まれるだろう)に交渉しながら、経過する時間と刻々と変化する諸環境(物理的、概念的、想像的)を線的に横切っていくというイメージになる、とわたしは考えている。
- 6∧「ノイジーな身体」は、岡田/チェルフィチュ自体が、その活動を紹介するときに頻繁に使う表現である。たとえば、現行のチェルフィッチュのHPには、以下の記述がある。「現代を代表する演劇カンパニーとして国内外で高い注目を集める。その日常的所作を誇張しているような/していないようなだらだらとしてノイジーな身体性は時にダンス的とも評価される」(https://chelfitsch.net/profile/)。また、外部の評論家・研究者も、類似の表現を使うことがある。ネット上で確認できるものとしては、木村覚による「超口語演劇」のartscape/Artword(アートワード)における定義があり、そこで木村は、「岡田は、言葉のリアリティを確保するだけではなく、そうした言葉をしゃべることで引き出されてくる、無意識状態の身体のノイジーで無駄な動き、すなわち日常の身体がもつ過剰性を舞台に導入した」と書いている(Kimura 2018)。
- 7∧日本語圏のいわゆるアングラ・小劇場演劇における演技と俳優の主体の問題については、後述する「委任されたパフォーマンス」的側面における当事者(性)の問題もからみ、また、時代によって、あるいは実践家の方法意識によって、相当な揺らぎがあるため、歴史的に詳細な検証がなされる必要がある。ただ一般論として、レイノルズ的に言ってしまうことが許されるなら、「すでにもっている自身(わたしになる(becomings -me))のイメージと構成を維持し続けるための、欲望に駆動された変容の諸プロセス」としての「なること(becomings)」が、その中心的実践理念としてあったと考えられてよいと思われる。すなわち、登場人物に「なる」という西洋近代演劇の規範ではなく、わたしに「なる」(あるいは、わたしであり続ける(becomings-me))が、その演技主体の目的論的可能性の中心と見なされたと言えるのではないか、とわたしは考えている。したがって、そこでもやはり、「なってしまうこと(comings-to-be)」、あるいは「ノイズ」は、基本的には排除されるべき要素であった。ただし、例外的に「なってしまうこと(comings-to-be)」を自己目的化して「暴走」させる実践家も存在していたというのが、わたしの現時点での見解である。
3.ポストドラマ演劇/パフォーマンス的転回から「委任されたパフォーマンス」へ
前節では、岡田の微細にいたるまで徹底して発展しつづけるとみなされている方法論的思考につき、普遍的な語彙で理論化した松井を出発点とし、より原理的な思考を展開するレイノルズの議論にしたがって、論を進めてきた。ここからは、一端迂回をするようだが、本論考の主題、すなわち、「ヨーロッパ・フェスティヴァル文化から岡田利規/チェルフィッチュが受けた歓待」について、演劇論的分析を離れ、より文脈固有な環境、すなわち受容/歓待する側の歴史的・知的環境を明らかにするために、1968年以降、大きな変化が起きたと多数が同意するパフォーマンス文化をめぐる学問的圏域における、主として北米と大陸ヨーロッパにおける、理論的展開という問題について、まずは見ておくことにする。
ここで注目しておくべきことは、この時代についての主要な理論的ナラティヴは大西洋の西側、すなわちアメリカ合衆国から到来したわけではない、ということである。というのも、その圏域で登場しつつあった理論家/アーティストは、変化しつつある演劇の原理や実践に理論的、言説的に応接してその変化について書くことよりも、作品中でパフォームする、ないしはクリエーションを行うことに熱心だったからである。こう書くわたしは、すでに言及したリチャード・シェクナーという人物の、個人的ではあるが歴史的に意義のある動きを念頭に置いている。1962年、アメリカ合衆国のルイジアナ州ニューオーリンズにあるテューレーン大学から英文学で博士号を取得し、英文学者として出発したシェクナーは、次第に、パフォーマンスの創作へとその力点を移していく。さらに、1980年、自ら創立にかかわったパフォーマンス・グループを離れると、今度はニューヨーク大学大学院において、パフォーマンス研究という新たな学問分野の立ち上げに尽力することになったのである。その結果、少なくともアメリカ合衆国における演劇研究の風景は一変したと言ってよい8。
一方、フランスとドイツを中心とするヨーロッパ大陸においては、公共劇場という制度が、20世紀のあいだに、完全にエスタブリッシュされた制度として成立することになっていた。そこでは、日本語では文芸部員と訳されることが多かったドラマトゥルクが所属する部署が常設されることも珍しくなく、世界の他のどの地域よりも演劇の制度的強靱さを誇っていたため、大きな変化が言説的に可視化されるのは1990年代後半になってからである。それは、ハンス=ティース・レーマン(Hans-Thies Lehmann)による『ポストドラマ演劇(Postdramatisches Theater)』の出版(1999)9、さらに、エリカ・フィッシャー=リヒテ(Erika Fischer-Lichte)による『パフォーマンスの美学(Ästhetik des Performativen)』の出版(2004)10によってだと考えられている。北米と大陸ヨーロッパにある歴史認識的時差については、わたし個人が必ずしも興味をもっているわけではないが、当時、北米とヨーロッパ大陸を往還するようなインターカルチュラルでトランスコンティネンタルな動きをしはじめていたわたしを含む多くの研究者にとっては、この落差は確かに、字義通りの時差ボケ体験のように感じられていたたことはまちがいない。
それはともかく、本論が注目すべきなのは、大西洋の両側のあいだで起きた理論の活発な想像上の言説的交換―たとえば、よく知られた〈パフォーマンス〉か〈シアトリカリティ〉かといった批評研究の鍵概念をめぐる論争11―に実はとどまらないことである。というのもわたしは、まだ十分に認知されていないが、パフォーマンス研究/演劇研究と視覚文化/美術研究との学際的な交換も活発化していたと考えているからである。こうした潮流があって、近年、若手の研究者から興味深い刺激的な視点が提供されつつある。より具体的には、セバスチャン・ブロイ(Sebastian Breu)という若手研究者がその未出版のエッセイ(Breu 2015)において、クレア・ビショップ(Claire Bishop)の言説に、わたしの注意を向けてくれたのである。視覚文化研究者としてのビショップは、その著作において、一般にはパフォーマンス研究の研究対象に含まれると考えられる作品や諸主題を幅広く論じているのだ。フィッシャー=リヒテが2004年に「パフォーマンス的転回」という名称を、かなり遅れて、あるいはようやく、演劇実践の新潮流に与える一方で、ビショップは2006年の段階で―そのエッセイは『人工地獄(Artificial Hells)』(2012)に収められている―「社会的転回」という表現を、1989年のベルリンの壁崩壊以降、視覚文化で注目を集めるようになった「参加型アート」と一般に呼ばれるジャンルに批評的なアプローチをするための理論的フレームとして提出しているのである。
岡田/チェルフィチュのヨーロッパにおける受容にとっては、これまで本論で論じてきたことからも明らかなように、レーマンの「ポストドラマ」、あるいはフィッシャー=リヒテの「パフォーマンス的転回」なる歴史的局面が深くかかわっていることは、ほとんど自明なことであろう。岡田による上演のマテリアリティの複雑化というプロジェクトは、まずもって、上演の特権化、あるいは、上演=パフォーマンスの時空で生起する事象=パフォーマンスへの作家的注視の典型的な事例だと考えられるからである。ただ、岡田が指し示す「転回」には、ビショップ的「社会的転回」との関係も見てとれるのではないか。
その文脈で、重要な議論が展開しているのが、ビショップの著作の第八章にある「委任されたパフォーマンス―正当性をアウトソースする(Delegated Performance: Outsourcing Authenticity)」である。「ポスト89年の時代において」とビショップは書く。わたしたちが目撃したのは:
さらに彼女はこの傾向について、こう続ける。
もちろん彼女は直後に、これは演劇や映画を制作する伝統的ないしは確立した方法とは異なると付言している。というのも、こういう類いのパフォーマンスは「自身の社会経済的カテゴリー―それがジェンダー、階級、エスニシティ、年齢、障害、あるいは(より稀であるが)職業に基づいたもの―をパフォームするために人びとを雇うのである」(同上)。誰もが想像できるように、また実際ビショップ自身も他の箇所で明示しているように、この傾向は、ハイアートの美術家とその批評的、学術的、ジャーナリズム的環境における表象の危機意識から出現したものである。
ビショップによる「委任されたパフォーマンス」という理論が魅力的なのは、ここに、岡田/チェルフィッチュもその圏域に存在すると思われる、日本語圏のいわゆる小劇場演劇と共通する特徴や要素が数多く観察可能だからである。1960年代後半に出現するアングラ演劇にその淵源を持つとされる小劇場演劇は、周知のように、今や独立したジャンルとして認知され、伝統―他のジャンルとは峻別可能な方法論や美学、社会との関係意識、政治意識等々―を作ってきたと考えられる演劇実践である。
ここでビショップの議論をもう少し詳しく見ておこう。こうした「委任されたパフォーマンス」においては、
あえてパラフレーズする必要もないだろうが、ここで主題化されているのは当事者性の問題である。もちろん、「社会的転回」においては、その当事者性は、「社会的に周縁化された構成体」、すなわち、いわゆる社会的弱者の当事者性である。したがって、そこに参加するパフォーマーはプロではなく(「プロではないパフォーマーを雇用する」)、その真正性を保証するのは、パフォーマンスの芸術的〈強度〉ではなく、当事者という〈事実性〉になるというのである。その結果、自明のことながら、モダニズム的真正性が美学的〈強度〉を交換価値としていたとするなら、「社会的転回」以降のパフォーマンスにおいては当事者への〈共感〉が、交換価値となる。「反駁不能」(=共感しないという選択肢がない)な「鮮烈な」「真正性」である。
こうしてみると、ここで書かれていることは、日本の小劇場演劇が機能しているその道筋と酷似しているということに驚くほかはない。それも、平田オリザの現代口語演劇登場以降は、特にその傾向を強めているのではないか。アングラ演劇の特色のひとつは、それに先立つ新劇における職業俳優・職業アーティストという存在へのアンチテーゼとしての、その素人性にあった。そこでの交換価値は、上演の〈強度〉というより〈共感〉である。ただし、アングラの時代には、唐十郎の「特権的肉体論」というテーゼが示すような弱者の逆説的強度が価値とされていた―よく知られているように、唐の特権性は、弱者が強者を見返す視線に胚胎される特権性である12―のに対し、現代口語演劇以降は、ワークショップ全盛という事態を背景としつつ、誰でも俳優になれる時代になったために、上演の交換価値は紛れもなく〈共感〉へと絶対的、不可逆的にシフトしたのである。日本の小劇場演劇こそ、ポストモダンの「参加型アート」/「関係性の美学」の先駆、いや、先駆はいいすぎだというなら、ヴァリアントにほかならないのである13。
ただし、本論の趣旨にとって重要なことは、主として英語圏で活動する現代美術研究者であるビショップが、意図せず日本の小劇場演劇を理論化してしまったことなどではない。そうではなくて、ここで彼女が理論化してみせるような事態が、大陸ヨーロッパのハイアート実践として伝統的にカテゴリー化されてきた領野で、広範に認知可能な過去30年間の文脈的環境としてあるとするなら、こうした地域において、演劇観客がもつ文化的に正統化された期待値の一部を、ビショップ的「委任されたパフォーマンス」にまつわる諸属性/諸要素が担っていると考えるのは、的外れなのかという問いが重要なのである。日本語圏とは異なり、少なくとも大陸ヨーロッパにおいては、演劇観客は、伝統的なあるいは革新的な現代美術の展覧会、展示やパフォーマンス・イベントやプロジェクトの観客でもある可能性が高いといってもよいのではないか。したがって、岡田/チェルフィッチュの作品が世界のどこよりも先に、大陸ヨーロッパで評価されたのは、観客として想定可能な人びとが存在する社会文化政治的文脈における、ビショップ的「委任されたパフォーマンス」への「社会的転回」が寄与していたと考えてもよいと思えるのである。
ただし、だからといって、岡田の劇作家・演出家としての〈権威=創造性〉を否定しようというのではない。それよりむしろ、ビショップを再び引用するなら、岡田は「高次に演出された真正性のフォルムをたちあげるのだ。作品のコントロールをパフォーマーたちに委任することで、単独的な作家性には疑問符がつけられる。参加者はリアリズムを保証するが、それは、その正確な結果が予測不能である高次に作為的状況を通じて行われるのである」。レイノルズの「横断=貫網的演技」の不可避の痕跡としての予想不可能性が、岡田のほぼすべての作品の署名性とでも呼べるものになっており、他方で彼の俳優たちは、「登場人物」を表象したり行為化することを自己目的化するのではなく、「自身」を演じ/パフォームすることで、「わたしではない……わたしではないではない」の存在論を、上演の瞬間瞬間に、身体化/現実化しながら(=「瞬間瞬間の具体的現れをする(instantiates emergently)」)、日常的な存在から乖離したドラマ内人物ではなく、「横断=貫網的諸主体」として、字義通りに網状にある諸カテゴリーを線的に横断しつつも、「委任されている」という諸感覚をも発しつづけるのである。
- 8∧このあたりの記述については、日本語文献ではたとえば、高橋雄一郎『身体化される知―パフォーマンス研究』(2005、せりか書房)、あるいはより簡便な解説としては、高橋雄一郎「パフォーマンス」(『パフォーマンス研究のキーワード―批判的カルチュラル・スタディーズ入門』(2011、世界思想社、15~50頁)がある。
- 9∧ハンス=ティース・レーマン(1944~)はドイツの演劇学者。ギーセン大学(1981~87)で革新的な演劇学の講座を担当し、その後、フランクフルト大学で2010年まで教鞭をとった。その主著のひとつ『ポストドラマ演劇』は、原著出版(1999)からあまり時間をおかずに、また英語版(2006)よりずっと早く日本語訳が出た(2002)。当時はちょうど、フェスティバル/トーキョーやその前身にあたる東京国際芸術祭に、ヨーロッパから先鋭的(と見なされうる)作品が相次いで来日し、また同時に、日本語圏のゼロ年代演劇が〈新しいもの〉として認知されるという時代環境があり、「ポストドラマ演劇」という語は、またたくまに人口に膾炙していった。実証的なデータは持ち合わせていないが、わたしはそういう印象で、それほどまちがってはいないと思う。それには、レーマン自身がフェスティバル/トーキョーからの招聘を含め、毎年のように来日していたという事実も関係していよう。本書においてレーマンは、「七〇年代以降において」「日常生活におけるメディアの普及と遍在を背景に、本書でポストドラマ演劇と名づけるような、多様な新しい演劇的な言説様式が登場してきているのではないか」(和訳23頁、強調は原著者)と書いている。すなわち、同時代舞台芸術における、ドラマ・テクスト(=戯曲)が必ずしもその中心にはない多様な上演の方法ないしは話法を包括する概念として「ポストドラマ演劇」という呼称を提出しているのである。したがって、その概念は、「あの『画期的な』概念である『ポストモダン』の時代性とは対照的に、具体的に演劇美学的な問題設定である」(21頁)とし、「ポストドラマ演劇というパラダイム」(25頁、強調は原著者)とも呼んでいる。つまり、演劇というジャンルを枠づける時間や空間、言語、音や視覚イメージ、あるいは、俳優とその身体、観客、劇場といった諸概念に大きな変更が加えられ、演劇作品の創造及びその受容・評価が、従来とは異なる基準ないしは価値観に依拠するようになったというのである。ドラマ・テクスト(=戯曲)を素材とし、登場人物に扮した俳優が、基本的にはリニアに進行する(=終わりと始まりがある)物語を演じるさまを、劇場空間であるとアイデンティファイ可能な空間/舞台で上演し、それを観客が鑑賞するという伝統的な演劇の形態が、メインストリーム(=「自然」/「当然」)では必ずしもなくなったのである。レーマンが不完全だとしながらもあえて作成したポストドラマ演劇の実践者固有名の長大なリストが、アメリカ合衆国出身のロバート・ウィルソン(1941~)で始まる(同上24頁)ことから、アメリカの1970年代に出現した「イメージの演劇」(ボニー・マランカによる)が、ヨーロッパ的な意味での伝統的なドラマ演劇から「ポストドラマ演劇」へのパラダイムシフトを理論的に要請したことが象徴的に見てとれる。なお、ネットで簡単に読める専門家による「ポストドラマ演劇」の解説については、簡便な解説として、新野守宏「ポストドラマ演劇とは?」(2008)(https://www.nntt.jac.go.jp/centre/library/society/society09.html)、また論考として同著者による「ドイツ語圏の演劇のポストドラマ的な傾向について」(2010)(https://ci.nii.ac.jp/els/contents110007590280.pdf?id=ART0009408921)がある。
- 10∧エリカ・フィッシャー=リヒテ(1943~)は、ドイツの演劇学者。フランクフルト、バイロイト、マインツの大学で教鞭を取った後、1996年からベルリン自由大学人文学部演劇学科主任教授をつとめるなど、ドイツにおける演劇研究を主導。2002年からはドイツ学術振興会の特別研究チーム「パフォーマンスの諸文化ー中世、初期近代、現代におけるパフォーマンス的転回」の座長、08年にはベルリン自由大学にパフォーマンス・カルチャーの国際的な研究センター「諸パフォーマンス文化を縫い合わせる(Interweaving Performance Cultures)」を立ち上げてもいる。さて、ここで言及している『パフォーマンスの美学』は、アメリカ合衆国におけるパフォーマンス研究の発展、あるいはパフォーマンス/パフォーマティヴという概念それ自体の哲学的展開に応答するかたちで書かれている。そのことは、冒頭、マリーナ・アブラノビッチのパフォーマンス(『トーマスの唇』、1975年)から議論が開始されることでも明らかだろう。しかもフィッシャー=リヒテは、この75年のパフォーマンスにつき、「主体/客体関係や、素材・身体の位相とシニフィアンの位相の関係が新しく定義づけられるという芸術的出来事は、「トーマスの唇」が唯一でも最初でもない」とし、「一九六〇年代初頭、欧米文化の諸芸術においてパフォーマンス的転回が始まったことを見過ごしてはならない」(和訳22頁)と言うのである。「この転回は、諸芸術のそれぞれにおいてパフォーマンス的なものへの移行をもたらしただけでなく、新しい芸術ジャンル、すなわちアクション・アートやパフォーマス・アートの形成につながるものだった」(同上)とも彼女は書いている。こうして本書は、パフォーマンス的転回の精緻な理論化へ、さまざまな具体例とともに、歩を進めていく。ここで注意すべきは、フィッシャー=リヒテが、欧米を同じ圏域として扱うことができている点であり、その点でも、レーマンの「ポストドラマ演劇」とシェクナーの一連のパフォーマンス研究にかかる諸著作を受けてこそ書かれえた書物という感が強い。ただし、本書ではカタログ的に多くの固有名が登場するのではなく、上演の美学を構成する諸要素について精密に検討するという理論的思考が中心になっている。すなわち、俳優と観客をはじめ、第4章「素材性のパフォーマンス的産出」で扱われる「身体性」「空間性」「音響性」「ライヴ性」、あるいは、第5章「意味の創発」における「意味」の問題、といった具合である。訳者・中島裕昭が「解説」で注意喚起してくれているように、本書は、「パフォーマンスの理論としては実は後発のものであるので、先行研究を参照しながら新たな論点のみを加えるという叙述が可能だったはずだが、実際にはそうなっておらず、むしろ、新しい芸術実践を前にしてそれらをどう解釈すべきか、先入観を除いて観察し、記述し、問題を明らかにし、これまでの理論を参考にしながら考察し、新しい概念を獲得」(329頁)しているのである。
- 11∧この〈パフォーマンス〉か〈シアトリカリティ〉かという論争の経緯については、わたしがリチャード・シェクナーに行ったインタビューの中でも触れられている。なお、このインタビューは、シェクナーがかかわった部分のパフォーマンス研究の成立にかかる経緯についても詳しい(Uchino 2005)。
- 12∧周知のように、唐十郎「特権的肉体論」(1983〔1968〕)の「いま劇的とはなにか」において、独特の詩的イメージで語られる特権的肉体の主は中原中也という「病者(びょうじゃ)」(3頁)であり、「東北の農村」の「八〇才の頑強な婆さん」(13頁)であり、「それは、見つめられればられるほど、傷つけられれば傷つけられるほど、そこから血しぶきの由来を語る花だ」(11頁)。「特権的肉体とは、特権的に肉体の在りかを凝視していたものと、凝視されていたものということになる」(14頁)と書かれている。
- 13∧このあたりの記述について、牽強付会だという意見があるかもしれない。アングラ演劇は、明らかに社会的他者としての〈弱者〉―共同体の他者、あるいは外部の〈マレビト〉/芸能者―という自意識だったと思われるにしても、である。平田オリザ以降の、いわゆる一般市民による演劇実践について、〈弱者〉どころかメインストリーム(=中産階級)であることは、客観的には明らかである。しかしながら、新劇を含む戦後演劇は一貫して―おそらくゼロ年代の前までという限定が今は必要だろうが―〈大衆〉や〈庶民〉をアイデンティティ、つまりはビショップ的「社会的に周縁化された構成体」として主体化しているように見えることを忘れるわけにいかない(繰り返しになるが、客観的に見れば、周縁化などされてはいないにもかかわらず、である)。その際の、〈大衆〉・〈庶民〉は、事実上の多数派であっても、第二次世界大戦敗戦以降に生成された「被害者共同体」の構成員(エージェンシー)として、アイデンティファイされている―意識的であれ、無意識的であれ―場合が多いように思われる。だからこそ、〈強度〉ではない〈共感〉が交換価値となるのである。〈強度〉は、舞台と観客席を分断するが―あるいは、ジャック・ランシエール的に観客を解放させるが―〈共感〉は一体化させるのである。このあたりについては、さらに議論すべき問題だと考えるので、稿を改めて論じたい。
結語
本論ではまず、2007年にはじまる岡田利規/チェルフィッチュの大陸ヨーロッパのフェスティヴァル文化における熱狂的な受容につき、松井みどりとわたし自身のこれまでの論考を先行研究として紹介した。そこで重要なコンセプトとして登場した「流動的な主体」(ドゥルーズ/松井)と、「トランスナショナルで一時性の諸主体」(内野)について、ブライアン・レイノルズの「横断=貫網的演技」の理論を導入することで、岡田/チェルフィッチュによる上演空間の複雑化について、より具体的な検討を行うことになった。レイノルズによる「なること(becoming)」と「なってしまうこと(comings-to-be)」の弁証法的というより横断性の、あるいは貫網性のプロセスとしての演技論/上演の理論は、リチャード・シェクナーの俳優の存在論(「わたしではない(not myself)……わたしではないではない(not not myself)」)とも響き合いながら、演劇というものの普遍的現象あるいは原理を説明するモデルであるとひとまずは考えられる。そのとき、岡田/チェルフィッチュは、近代演劇のイデオロギー内では抑圧されるべきだとされた、「なってしまうこと(comings-to-be)」を、反近代の身ぶりとして暴走させるのではなく、意図的/戦略的に上演に導入することで、「ノイジー」という感覚を生起させているのではないか、と論じた。
引き続き本論では、北米発のパフォーマンス研究と大陸ヨーロッパを中心とする伝統的な演劇研究の対立から生じる奇妙な時差/落差に言及しつつ、「ポストドラマ」(ハンス=ティース・レーマン)や「パフォーマンス的転回」(エリカ・フィッシャー=リヒテ)という大陸ヨーロッパのパフォーマンス理論史的展開が、岡田/チェルフィッチュの受容と関係していると指摘した。さらに、美術批評家であるクレア・ビショップによる「委任されたパフォーマンス」という、近年の現代美術における主要な動向によって醸成されている、〈共感〉を交換価値とする観客の期待値もまた、岡田/チェルフィッチュの受容とかかわっているのではないかとも論じることになった。
以上、わたしが2007年以来、一貫して分節化を試みてきた、岡田利規/チェルフィッチュの大陸ヨーロッパのフェスティヴァル文化から受けた、歴史的に前例のない熱狂的な歓迎につき、ある程度の分析的観察と理論的考察ができたのではないかと考えている。もちろん、わたしがぐずぐずしているうちに、岡田/チェルフィッチュは進化/深化をつづけ、『あなたが彼女にしてあげられることは何もない』(2015)、『部屋に流れる時間の旅』(2016)、『三月の5日間』リクリエーション(2017)といった日本語圏での上演を前提にした作品のみならず、日韓共同制作の『God Bless Baseball』(2015)といった国際共同制作にも積極的に取り組んでいる。それ以上に画期的なのは、ドイツ・ミュンヘンのカンマーシュピーレにおける四年連続のレパートリー作品の制作である。現段階で『ホットペッパー、クーラー、そしてお別れの挨拶』(2016:初演は2009年)、『NŌ THEATER』(2017)、『NO SEX』(2018)の三作品が上演されており、現在、第四作目が―純粋の書き下ろしとしては三作目―が構想中であるという。岡田/チェルフィッチュの非日本語圏における受容は、すでにもう、論文の主題にすらならないほどの当然の前提となってしまっており、これ以降は、では、それぞれの上演/プロジェクトで、いったいなにが達成されたのか/されなかったのか、といった水準での論考が書かれるべき時代になっている。わたし自身、個別の作品論を書くべきだと思っているし、いつになるか確証はないが、また、わたしが適役であるかどうかも不明だが、岡田利規の包括的な作家論が書かれるべき段階に入っていることは、まちがいないところなのである14。

- 14∧ドイツ・トリアー大学においてで2016年8月5日~7日の日程で開催された国際研究集会「現代日本における芸術と社会―岡田利規の演劇 (Art and Society in Contemporary Japan: The Theatre of Okada Toshiki)」は、岡田本人も参加し、ほぼ個別の岡田作品を扱う12の研究発表が並ぶ画期的なものであった。この学会の成果については、英語での出版予定があると聞いているが、学会内容の簡便な紹介については、拙稿「ドイツでの『岡田利規』学会(「新潮」十月号、2016)208~9頁を参照のこと。
*本論は、以下の学会における英語の発表原稿をもとにしている。第87回日本英文学会全国大会における招聘パネル(“Towards Transnational Mobilities: On Questions of Body’s Border Crossings”)、2015年5月24日東京・立正大学。発表題目は、“Simultaneous Turns in Globality: Performative and Social Turns in the New Millennium, or Theorizing/Historicizing Okada Toshiki’s Welcome to European Festival Cultures”であった。引き続き、加筆修正した原稿を同題目で、ドイツ・トリアー大学において2016年8月5日~7日の日程で開催された以下の機会に行った。「現代日本における芸術と社会―岡田利規の演劇 (Art and Society in Contemporary Japan: The Theatre of Okada Toshiki)」。本論は、その第二稿を日本語訳しつつ、大幅に加筆修正を行ったものである。
参考文献
-
Bishop, Claire.
- 2012
- Artificial Hells: Participatory Art and the Politics of Spectatorship. London: Verso. 邦訳『人工地獄』大森俊克訳、フィルムアート社、2016年。
-
Breu, Sebastian(セバスチャン・ブロイ)
- 2015
- 「ヴァイラル・パフォーマンスの散乱体-クリストフ・シュリンゲンズィーフ『オーストリアを愛して!』と公共圏の演劇化」(未出版)
-
Fischer-Lichte, Erika(エリカ・フィッシャー=リヒテ)
- 2004
- Ästhetik des Performativen. Franfurt am main: Surhrkamp Verlag. 邦訳『パフォーマンスの美学』、中島裕昭他訳、論創社、2009年。
-
Lehmann, Hans-Thies(ハンス=ティース・レーマン)
- 1999
- Postdramatisches Theater. Frankfurt am main: Verlag der Autoren. 邦訳『ポストドラマ演劇』、谷川道子他訳、同学社、2002年。
-
Harding, James Martin and Rouse, John (eds.)(ジェイムス・マーティン・ハーディング及びジョン・ラウス編集)
- 2006
- Not the Other Avant-garde: The Transnational Foundations of Avant-Garde Performance. Ann Arbor: U. of Michigan P.
-
Kara, Juro (唐十郎)
- 1983(1968)
- 『腰巻きお仙 特権的肉体論』。現代思潮社。新装版。
-
Kimura, Satoru (木村覚)
- 2018
- 「超口語演劇」アートワード、「artspace」
http://artscape.jp/artword/index.php/%E8%B6%85%E5%8F%A3%E8%AA%9E%E6%BC%94%E5%8A%87
-
Matsui, Midori(松井みどり)
- 2011
- 「両面通行-グローバル化時代の国際展と日本の現代美術の受容」。『表象』第五号、月曜社、59~74頁。
-
Niino, Morihiro (新野守宏)
- 2008
- 「ポストドラマ演劇とは?」。
https://www.nntt.jac.go.jp/centre/library/society/society09.html
- 2010
- 「ドイツ語圏の演劇のポストドラマ的な傾向について」。
https://ci.nii.ac.jp/els/contents110007590280.pdf?id=ART0009408921
-
Ozaki, Tetsuya (小崎哲哉)
- 2002
- 「Out of Tokyo 126: ジャンルの問題」
http://archive.realtokyo.co.jp/docs/ja/column/outoftokyo/bn/ozaki_126/
-
Reynolds, Bryan (ブライアン・レイノルズ)
- 2009
- Transversal Subjects: From Montagne to Deleuze after Derrida. London: Palgrave Macmillan.
-
Slagmuylder, Christoph (with Uchino Tadashi and Okada Toshiki) (クリストフ・スラフマイルダー)
- 2008
- 「基調講演:同時代の舞台芸術」。コンテンポラリー・パフォーミングアーツ TPAM-IETM 採録集。
https://www.tpam.or.jp/pdf/ietmreport_j.pdf
-
Takahashi, Yuichiro (高橋雄一郎)
- 2005
- 『身体化される知―パフォーマンス研究』。せりか書房。
- 2011
- 「パフォーマンス」。高橋雄一郎・鈴木健編著『パフォーマンス研究のキーワード―批判的カルチュラル・スタディーズ入門』、世界思想社、15~50頁。
-
Uchino, Tadashi(内野儀+住友文彦+ジャックリーヌ・ベルント+アレクサンダー・ツァールテン+加治屋健司)
- 2011
- 「共同討議 文化のナゴシエーションと日本-トランスメディア、トランスカルチャー、トランスネーション」。『表象』第五号、月曜社、18~58頁。
-
Uchino, Tadashi(内野儀)
- 2004
- 「Jと世界を語り直す――チェルフィッチュ『三月の五日間』」。「Jの風景(6)」、「演劇の現在」、「図書新聞」3月27日号、図書新聞社、8頁。
- 2005
- 「パフォーマンス研究の起源と未来――リチャード・シェクナーに聞く」。『舞台芸術』第八号、京都造形芸術大学舞台芸術研究センター、12~40頁。
- 2008
- 「『グローバリゼーションは身体に悪い』、あるいはトランスナショナルな埒外(オープン・スペース)で共振するポストヒューマンな身体について」。『劇場文化』第一二号、財団法人静岡舞台芸術センター、82~92頁。
- 2010
- 「村上春樹を上演(perform=embody)するために――〈いま、ここ〉のマテリアリティの複雑化ということ」、『ユリイカ』一月臨時増刊号、青土社、183~191頁。
- 2015
- “’Database Animals’ and the Avant-garde: Materializing Transnational, Transient Subjectivities in Posthumanity.” Unpublished manuscript.
- 2016
- 「ドイツでの『岡田利規』学会」。『新潮』十月号、新潮社、208~9頁。